令和5年度「過労死等の労災補償状況」公表の公表
厚生労働省から、令和5年(2023年)の過労死等の状況の発表がありました。
過労死等に関する請求件数は、4,598件と前年度比1,112件の増加です。
また、支給決定件数は1,097件であり、前年度比193件の増加です。
うち死亡・自殺(未遂を含む)件数 135件前年度比14件の増加です。
請求件数、支給決定件数も過去最多です。
(なお死亡の件数はもっと多い時がありました。)。
脳・心臓疾患
請求件数は1,023件で、前年度比220件の増加。
うち死亡件数は前年度比29件増の247件。
支給決定件数は214件で前年度比20件の増加。
うち死亡件数は前年度比4件増の58件。
精神障害
請求件数は3,575件で前年度比892件の増加。
うち未遂を含む自殺の件数は前年度比29件増の212件。
支給決定件数は883件で前年度比173件の増加。
うち未遂を含む自殺の件数は前年度比12件増の79件。
すべてにおいて、2022年を上回っています。
厚生労働省は、増加した原因について次のように述べています。
「厚生労働省の担当者は、「脳や心臓の病気については、55歳以上の労働者が増えたことが関係していると考えられる。また精神疾患については、過労死やパワハラへの認識、理解が進んだため、申請が増えたのではないか」と説明しています。」(日本テレビニュースより)
脳・心臓疾患については令和3年に認定基準が改定されています。また、精神障害は、令和5年9月に認定基準が改定されています。その影響もあったのではないかと考えられます。
認定率は
脳・心臓疾患 全体の認定率は 32.4%(昨年は38.1%)
死亡の認定率は 31.0%(昨年は32.1%)
精神障害 全体の認定率は 34.2%(昨年は35.8%)
自殺の認定率は 46.5%(昨年は43.2%)
脳・心臓疾患の認定率が2023年より下がっているのが気になります。死亡については過去5年で最低です。
自殺の認定率は高くなっています。
なお、愛知県のデータを見ると
脳・心臓疾患 請求件数は77件、うち死亡は13件
支給決定件数は15件、うち死亡は3件
精神障害 請求件数259件 うち死亡は17件
支給決定件数は62件 うち死亡は4件
という状況です。やはり精神障害が多いですね。自殺の認定数が請求件数に比べて少ないように思います。
2024年6月15日(土)「過労死・ハラスメント労災110番」全国一斉電話相談を実施します
2024.6.15(土)
過労死110番全国ネットワーク(主催) の 過労死110番を行います。
今年は「過労死・ハラスメント労災110番」と題して行います。
10:00-16:00
TEL 0120-777-654
※事前の問い合わせは、03-3813-6999
上記フリーダイヤルは、実施日時以外はご利用になれませんので、ご注意ください。
上記フリーダイヤルにおかけいただきますと、お近くの窓口につながります。
窓口によっては受電時間が異なる場合がありますが、 その場合は他の窓口につながるように設定されています。
本日の過労死110番は終了しました。合計30件の相談がありました。相談された方が、電話での相談により、今後につながることを祈念しております。(6月15日 追記)
名古屋過労死を考える家族の会
5月18日、名古屋過労死を考える家族の会の総会が開かれました。
過労死弁護団の一員として参加してきました。
今裁判を闘っているご家族。事件はおわって、久しぶりにお会いしたご家族。
何人もの方にお会いできて良かったです。
全国過労死を考える家族の会 » 全国各地の家族の会 (karoshi-kazoku.net)
皆さんで集まって出てくる話は、裁判官のこと。
皆さん、事案はそれほどかわらないのに、認められなかったり、認められたり。
裁判官はくじなのか。
そんな愚痴が出ました。
過労かどうか、最後は社会通念がどうか、みたいなところになるので、その裁判官の価値観、人生感が、結果に追う聞く影響する印象を持つことになるだろうと思います。
公立学校の教員の給与について
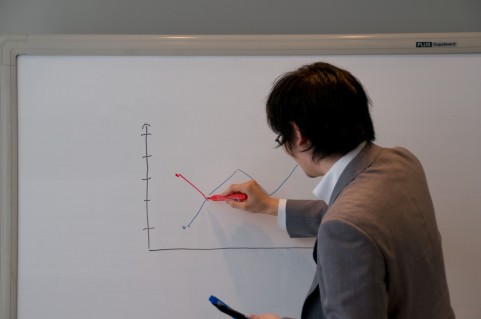
教員の給与のあり方や働き方改革を議論してきた中教審の特別部会は、残業代を支払わない代わりに支給している上乗せ分を、現在の月給の4%から10%以上に引き上げるべきだとする素案を示した、と報道されました。
公立学校の教員は、いわゆる「特級法」によって、事実上残業代が支払われません。
今回の素案は、この問題の制度を、上乗せ分を引き上げることにして、解決しようとしています。
これは、実質的に「固定残業代」と同じように、残業のすべてに残業代を払われないことになりかねず、問題を残すものです。
特級法の趣旨は、学校の先生の労働は、通常の労働と違って労働と労働でない時間の区別がつきにくいからと言われています。
しかし、私立学校の先生については労働基準法の適用があります。また、国立大学法人の附属の学校の先生についても、現在は国立大学法人の職員という立場にありますから、労働基準法の適用があります。特級法の適用はありません。したがって、残業代を支払う必要があります。
同じように学校の先生をして、私立や国立大学附属であれば、「仕事」と「仕事ではない」ことについて、厳格に区別する必要があり、公立学校の先生は、「区別がつきにくい」というのは、不合理と言わざるを得ません。
学校の先生の過労死等の事案は、報道されているだけでもたくさんいらっしゃいます。
公立学校の運営は、学校の先生の無償奉仕によって成り立っているといっても過言ではありません。
労働時間を管理し、時間外労働には残業代を支払う。労働時基準法の原則を適用する。このように運用することで、ようやく外の職場と同様に残業時間を短くする努力が本気で行われるのだと考えます。
少なくとも働いただけの賃金は先生に正当に支払われなければなりません。
残業を管理すると、残業を隠すようになる、と言われます。確かにそのような動きが一部に生じるかもしれません。
しかし、それはどの職場でも同じです。先生だけが特殊なわけではありません。
しかし、先生の命と健康(健康には心の健康もふくまれます。)を守るためには、まず、労働時間を把握し、残業代を支払った上で、削減の方法を考えるのが、正しい道筋だと思います。
時間外労働 2024年4月問題

現在、時間外労働の上限は上の図のように規制されています。
○原則として月45時間、年360時間(限度時間)以内
○臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間以内(休日労働含む)、限度時間を超えて時間外労働を延長で きるのは年6ヶ月が限度
2019年4月、このように規制する法律が施行されています。
ところが、この適用がない業種があります。
建設業、自動車運転の業務、医業に従事する医師等です。
2024年4月から工作物の建設の事業には適用されることになります。
2024年4月から、自動車運転の業務、医業に従事する医師の規制も始まります。
しかし、これらの業種の場合に、この規制が、とても緩いのです。
自動車運転の業務の場合、特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外労働の上限が年960時間となります。
これは、要するに、毎月、時間外労働を80時間、1年続けていいということになります。
過労死ラインは、発症前の2から6カ月間にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働時間数があるばあいに、労災と認めるというものですから、規制をまもったとしても過労死が発生する可能性があるというものです。
医師の場合にはもっと緩いです。
特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外・休日労働の上限が最大1860時間(※)です。
この1860時間というのは、時間外・休日労働の上限です。年間の労働時間ではありません。
なんと、1か月155時間時間外労働をしてもよいということになっています。
週40時間労働が労基法の原則です。1年は52週間と1日ありますから2088時間となります。これを1860時間超えて良いということは3948時間働いてもよいということになります。これを365日で割ると、10.8時間 =10時間48分
毎日、10時間48時間休みなく働いてもよいなどという規制は、規制の意味がないように思います。
早く、全ての仕事で過労死ラインが違法となるような規制が望まれます。
※特別条項付き36協定を締結する場合、特別延長時間の上限(36協定上定めることができる時間の上限)については、
A水準、連携B水準では、年960時間(休日労働含む)
B水準、C水準では、年1,860時間(休日労働含む) となります。
なお、医業に従事する医師については、特別延長時間の範囲内であっても、個人に対する時間外・休日労働時間の上限
として副業・兼業先の労働時間も通算して、時間外・休日労働を、
A水準では、年960時間/月100時間未満(例外的につき100時間未満の上限が適用されない場合がある)
B・連携B水準・C水準では、年1,860時間/月100時間未満(例外的に月100時間未満の上限が適用されない場合が
ある)とする必要があります。
新しい精神障害の労災認定基準が発出されました

1 新しい認定基準が見られる場所
2023年(令和5年)9月1日、新しい精神障害の労災認定基準が発出されました。厚生労働省のホームページに掲載されています。
下記のホームページからみることができます。
精神障害の労災補償について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
ここには新しい認定基準
どこがかわったかを説明している 留意点
があります。
認定基準のもととなった専門検討会の報告書
も報道発表のところに載っています。
2 発病後増悪の要件が緩和
新しい認定基準で、大きく変わったのは発病後増悪の問題です。
今までの認定基準は、
「別表1の特別な出来事があり、その後おおむね6か月以内に対象 疾病が自然経過を超えて著しく悪化したと医学的に認められる場合」にしか、「悪化した部 分について業務起因性を認め」ませんでした。
今回は、
「特別な出来事がなくとも、」「悪化の前に業務による強い心理的負荷が 認められる場合には、」
悪化した部分について業務起因性を認め」る可能性があることを認めました。
3 一回でも「執拗」(パワハラ)
また、パワーハラスメント等について「一定の行為を「反復・継続するなどして執拗 に受けた」としている部分があります。これは、「執拗」と評価される事案 について、一般的にはある行動が何度も繰り返されている状況にある場 合が多いが、たとえ一度の言動であっても、これが比較的長時間に及ぶものであって、行為態様も強烈で悪質性を有する等の状況がみられるときにも「執拗」と評価すべき場合があるとの趣旨である。」と認定基準に記載されました。
4 労働時間について
精神障害が認められる時間外労働の基準は長すぎると批判してきましたが、今回は、大きな改正はありませんでした。
5 カスハラの項目が入りました
「社会情勢の変化等を踏まえ、業務による心理的負荷として感じられる出来事 として新設された。」と新設の理由が説明されています。顧客や取引先、施設利用者等から、暴行、脅迫、ひどい暴言、 著しく不当な要求等の著しい迷惑行為を受けたことの心理的負荷を評価する項目です。
9月1日から新しい認定基準で運用が始まります。すでに労基署で調査している事案も新しい認定基準で調査を行います。
より適切に認められるように希望します。
2022年(令和4年)の「過労死等の労災補償状況」

厚生労働省が、2023年(令和4年度)の過労死等の災害補償状況を公表しました。
令和4年度「過労死等の労災補償状況」を公表します|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
1 脳・心臓疾患に関する事案の労災補償状況
(1)請求件数は803件で、前年度比50件の増加。
うち死亡件数は前年度比45件増の218件。
(2)支給決定件数は194件で前年度比22件の増加。
うち死亡件数は前年度比3件減の54件
(3)認定率
38.1% 昨年 32.8%
昨年よりアップしています。
うち死亡認定の認定率は
38.8% 昨年 33.7%
認定件数が多くなっているのは残念です。
死亡事案は減少しています。
その上で死亡事案も認定率はアップしています。
ただ、請求件数は、死亡事案も増えていますから、令和5年になって過労死認定の数も増えるのでは
ないかと心配されます。
認定基準が改訂されて1年たちました。その影響もあると考えられます。
2 精神障害に関する事案の労災補償状況
(1)請求件数は2,683件で前年度比337件の増加。
うち未遂を含む自殺の件数は前年度比12件増の183 件。
(2)支給決定件数は710件で前年度比81件の増加。
うち未遂を含む自殺の件数は前年度比12件減の67件。
(3)認定率
35.8% 昨年 32.2%
うち死亡認定の認定率は
43.2% 昨年 47.3%
請求件数、認定件数は増えています。請求件数が337件も増えているのはおどろきです。20年前
は、一年間の請求件数が300件を少し上回っていました。2001年は全体で264件の請求件数で
した。
認定されたものの多くは、パワーハラスメント、いじめ、いやがらせ、上司とのトラブルであり、こ
れらで全体の4割程度を占めています。パワーハラスメントをなくす対策が必要です。
なお、令和4年度に、審査請求、再審査請求、行政訴訟で,不支給が取り消された件数は
脳・心臓疾患は 9件 (うち死亡6件)
精神疾患は 25件 (うち死亡1件)
過労自殺案件で、審査請求、再審査請求、行政訴訟で取り消された件数は全国で1件しかありませんでした。
件数が減る方が望ましいのですが、増えているのは悩ましいところです。
これが権利を行使し、救済される件数が増えているので、どこかで過労死等が実際にも減少し、請求件数も減少していくといいとおもいます。当面は、さらなる救済を求めていくことが必要かと思います。
厚生労働省の発表を元にグラフにしてみました。
精神障害の請求件数と認定件数が年々上昇していることがわかります。
脳/心臓疾患はやや減少系傾向です。
中部電力事件 名古屋高裁2023年(令和5年)4月25日判決

2023年4月25日、名古屋高当裁判所民事第3部(長谷川裁判長)は、中部電力に勤務していた従業員が入社してわずか半年後の2010年10月末に自殺した事案で、名古屋高等裁判所は、過重労働を認めて、津労働基準監督署長の労災保険法に基づく遺族一時金の不支給決定を取り消す旨の判決をしました。
この判決は、この新入社員の従業員に対しパワーハラスメントが行われていたことを認めました。また、新入社員に、難易度の高い業務の主任を担当させ、十分な援助をしなかったことを認めました。
これまで、労働基準監督署長、労働者災害補償保険審査官、労働審査会、そして名古屋地方裁判所が認めなかった業務による自殺であることを名古屋高当裁判所が認めたのです。
この判決がなされるまで、当該従業員の方が自殺してから12年半、2013年に労災の請求をしてから10年の年月がたっています。
パワーハラスメントについては、亡くなった従業員が、生前に職場のことを職場外の友人知人や違う職場の同期に話していた内容が信用できるか、それがパワーハラスメントといえるかが問題になりました。この事件ではパワーハラスメントをした本人や、その周囲の先輩の同僚従業員が、その事実を否定しました。そのため、一審では、パワーハラスメントであることは否定され、心理的負荷の強度も弱とされてしまいました。しかし、控訴審では、職場外の友人に話していた事実について、十分に信用できるとされ、その内容も事実であると認められました。
次に、業務についてですが、一審では会社側の説明に沿って、新人にとって若干困難であってもその業務は、「強」とまではいえないとされていました。高裁では、担当していた業務について一つは「中」、そして最も困難であった業務については「強」としました。
新人にとって困難で心理的な負荷となるかどうかを判断するに際し、会社の説明は、どうしてもある程度経験のある者の説明となります。原告は、その説明は不当で、本来新人にとっては困難な業務であると主張してきました。高裁は、原告側にその内容を釈明しました。また、一審では採用されなかった中部電力のOBのかたの証人請求を採用し、当時の業務について立証の補充を認めました。
一審と控訴審では、業務について裁判官の見方が全く異なることになりました。
原告である母親は、本人に何があったかを知りたいと考え、会社の関係者に面談を求めました。知人、友人に会って話を聞き、本人が残したパソコンのメールをみて、資料を集めました。中部電力のOBの協力者に支援を求めました。
支援の会を結成し、多くの方に賛同を求めました。過労死防止の活動にも参加しました。
本当にやるべきことをすべてやり尽くした活動でした。
これらの地道な証拠の収集と裁判への運動に応えて、名古屋高等裁判所は、丹念に記録を精査し、証拠を採用し、業務の過重性を認めました。
原告の活動と、それを認めた高等裁判所、そして、それらをとりまとめた主任の森弘典弁護士に本当に敬意を表したいと思います。控訴審の尋問を担当した長尾美穂弁護士も尋問が判決つながりました。
弁護団は、森 弘典弁護士、長尾 美穂弁護士、そして当職です。
以下は弁護団が当日だした声明です。
2023年4月25日
声 明
中部電力新入社員労災裁判弁護団
本日、名古屋高等裁判所(民事第2部Ec係、長谷川恭弘裁判長)は、中部電力株式会社(当時)に新入社員として採用された26歳の労働者(以下「被災者」という)が入社して7か月も経たない2010年(平成22年)10月30日早朝(推定)に自死した事件で、津労働基準監督署長が業務外とした処分について、第1審の名古屋地裁判決を取り消し、業務外の処分を取り消す判決を言い渡した。
判決は、第1審判決と異なり、上司から被災者に対するパワーハラスメントを認定している。第1審判決は、被災者から上司の発言を聞いたという友人の証言があるにもかかわらず、伝聞に基づくものであることなどを理由として認めなかった。本判決は、友人の証言の信用性は高いと認め、証言内容も具体的などとして、パワーハラスメントを認定しており、密室で行われがちで、被災者が死亡している事案では直接体験した事実を語れる証人がいないパワーハラスメントの認定方法として重要な意義を有する判決である。
判決は、業務の過重性について、第1審判決と同じく平均的労働者基準説に立ちつつも、新入社員が未経験の業務を担当させられたという点に着目し、基準となる対象労働者を新入社員あるいは未経験者に限定して、業務の難易度を検討している。その上で、入社後わずか半年程度の新入社員でありながら難しい案件を主担当として行わなければならない状況を十分に考慮した指導や支援が行われていなかった状況を踏まえて、業務による心理的負荷を検討し、業務起因性を認めたものであり、極めて高く評価できる。
ほかの裁判例の中にも、平均的労働者基準説に立ちつつも、新入社員や未経験の業務という点に着目し、基準となる対象労働者を新入社員あるいは未経験者に限定して、業務による心理的負荷を評価するものがあるが、本判決はその論理が正しいことを裏打ちするもので、裁判例としても重要な意義を有する。
折しも、精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会では、心理的負荷の強度を客観的に評価するに当たり、どのような労働者にとっての過重性を考慮することが適当かが論点となっており、その内容を明確化するため、同種の労働者についての例を示すとともに、同種の労働者は一定の幅を内包することを明示してはどうかとの意見が示されている。そして、同種労働者についての例として、新規に採用され、従事する業務に何ら経験を有していなかった労働者が精神障害を発病した場合には、「同種の労働者」とするとの意見も示されている。
当弁護団は、厚生労働省、三重労働局長、津労働基準監督署長が本判決を真摯に受け止め、上告しないように強く求めるとともに、精神障害による過労死の認定基準の運用にあたって、新入社員、未経験業務の視点を考慮するとともに、今後の改定にあたっては、全面的に採用することを求める。
以 上
判決に対し、国は上告、上告受理申立てはせず、判決は確定しました。(2023年5月10日)
三重大学の過労死事件で記者会見を行いました
2022年12月28日、三重大学で勤務していた産科医の男性が死亡した事案が、過労死であり、労災であると認定された事案で、記者会見を行いました。
内容は報道されている通りです。亡くなった方にあらためて哀悼の意を表します。
新聞、テレビ局のニュースに取り上げていただきました。
2022年にこのような事件が報道された。今後は医師の働き方について考えなければならない。労働時間が適正になるように配慮しなければならない、と考え、防止につながる一助になればと願っています。
医師の時間外労働規制は、過労死が起きても、労働契約自体は適法となるような緩い基準しか考えられていません。それを改善することができないのは、医師が不足しているからだそうです。
過労死防止月間
11月は、過労死防止月間です。「過労死等防止対策推進法」により、定められています。
この月は、厚生労働省主催の過労死防止対策推進シンポジウムが各都道府県で行われます。
2022年も11月29日に岐阜市で、30日には名古屋市で開かれました。
今年は、どちらの会場でも佐戸未和さんのお母様にお話しを聞くことができました。
31歳NHK女性記者「過労死」8年苦しむ遺族の証言 | 未和 NHK記者の死が問いかけるもの | 東洋経済オンライン | 社会をよくする経済ニュース (toyokeizai.net)
佐戸さんは、NHKの記者。入局後9年目、31歳の若さでなくなりました。2013年7月でした。
それからまもなく10年が経とうとしています。
しかし、佐戸さんの御両親は、いまもいえることのない悲しみの中にいます。
今年の9月には、2019年におなじくNHKで働くかたが過労死と認定されたと報道がされました。
たしかにNHKはたくさんの方が働いているのでしょう。しかし、過労死の起きた組織で、他にも発生してしまった。
防ぐことはできなかったのでしょうか。
佐戸さんの死は、過労死防止のために、働き方を改革することはつながらなかったのでしょうか。
残念に思います。
あらためて、過労死はだれにでも生じる可能性があること。
そのことを多くの人に知ってもらいたいと思います。
2021年(令和3年)の過労死等の労災件数
厚生労働省が、2022年6月、令和3年度の過労死等の労災補償状況を公表しています。
令和3年度「過労死等の労災補償状況」を公表します|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
毎年、この時期に厚生労働省が過労死等の労災補償状況を公表しています。
令和3年(2021年)の特徴ですが、脳・心臓疾患の労災補償件数は、若干減少傾向です。
請求件数、認定件数も令和2年と比較して減っています。
そのうちの死亡については57件であり、減少傾向にあります。
認定率は、令和2年が29.2%だったのが32.8%と上昇しています。
このうち死亡の認定率も、令和2年が31.8%であったのが33.7%に上がっています。
なお、審査請求事案の取消決定は令和2年が6件だったところ、令和3年は15件となっています。
過去5年間でも最も件数が多くなっています。
一方精神障害については、請求件数が大幅に増えています。令和元年2060件で初めて2000件を超えました。令和2年2051件と若干増加でしたが、令和3年は2346件と300件弱も増えています。
支給決定件数は昨年の608件から629件に若干の増加です。
ただ、自殺案件は,令和2年の81件から79件に若干の減少です。
なお、申請九次案は、令和2年度25件、令和3年22件と多い水準で推移しています。
認定率は、令和2年が31.9%ですが、令和3年は32.2%と若干増加しています。
ちなみに自殺の認定率は令和2年が45.3%、令和3年は47.3%と高い水準で推移しています。
私の相談にのっているケースはなかなか認められないケースが多く、実感と少しずれている認定率ですが。
コロナウイルスの影響で、一部のとても忙しい人が心配ではありますが、全体としては仕事が減り、経済的に困る人が増えるが過労死等へ減るのではないか、と予想していました。しかし、そうではないようです。
コロナウイルスの影響がまだまだ続いています。
予想の付かない業務の変化で、心労を重ねたり、長時間労働が増える可能性もあります。
余裕のないところでパワハラが生まれることは最悪です。
今後も推移を見ていく必要があると思います。
、
2022年 過労死110番 6月18日土曜日

「過労死・ハラスメント・コロナ労災110番」
全国一斉電話相談を実施します
2022.6.18(土) 10:00-16:00
TEL 0120-800-591
電話番号は当日しかつながりません。
毎年6月に行っている過労死110番。今年は、「過労死・ハラスメント・コロナ労災110番」としておこないます。
昨年から全国一斉、フリーダイヤルで行っています。電話料も相談料も無料です。
東海地方では、愛知県、岐阜県、三重県にそれぞれ窓口があります。上記に電話していただければお住まいの県の担当者につながります。
パワーハラスメント防止措置
パワハラ防止措置が、中小企業の事業主にも義務化されました。
2022年4月1日、「労働施策総合推進法」によるパワーハラスメント防止措置が、それまでの大企業への適用だったところ、中小企業の事業主を含めてすえべての事業主の義務となったのです。
職場におけるハラスメントを防止するために、事業主がおこなわないといけないことは、法及び指針に定められています。事業主はこれらを実施しなければなりません。
1.事業主の方針を明確化し、管理・監督者を含む労働者に対してその方針を周知・啓発すること
2.相談、苦情に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備すること
3.相談があった場合、事実関係を迅速かつ正確に確認し、被害者及び行為者に対して適正に対処するとともに、再発防止に向けた措置を講ずること
4.相談者や行為者等のプライバシーを保護し、相談したことや事実関係の確認に協力したこと等を理由として不利益な取扱いを行ってはならない旨を定め、労働者に周知・啓発すること
5.業務体制の整備など、職場における妊娠・出産等に関するハラスメントの原因や背景となる要因を解消するために必要な措置を講ずること
これらの措置は、業種・規模に関わらず、すべての事業主に義務付けられています。
パワーハラスメントにあったときには、違法であり、慰謝料請求の対象となります。
また、パワーハラスメントにあったことにより、精神障害になり、通院、休養が必要となったときには、損害賠償の対象となり、事業主の責任を問うことができます。
しかし、実際には、パワーハラスメントが行われていないと争われたり、事実はあったがそれはパワーハラスメントと評価できないと争われたり、精神障害を発病させるほどひどいパワーハラスメントではないと争われることもあります。
パワーハラスメントが行われたことだけで慰謝料を請求しようとしても、その金額は大きくなく、実際に損害賠償請求することは、多くの場合に現実的ではありません。
一方で、パワーハラスメントと訴えられる前にパワーハラスメントで精神障害を発病し自殺に至る場合もあります。パワーハラスメント自体は精神障害を発病させるほどひどいものではなかったとしても、長時間労働や、困難な業務を命じられていて、それらが合わさって精神障害となり、不幸にも自殺してしまうケースもあります。
パワーハラスメントの対応が適切ではないことで二次的な被害として精神障害を発病させてしまうこともあり得ます。
パワーハラスメントはいけない、と言っているだけではこのような被害はなくせません。又、一旦起こってしまってもすべてが救済されるとも限りません。
ですから、パワーハラスメントが行われる前に、パワーハラスメントを誰もが起こさないように措置を講ずる必要があります。
あるいは行われてしまったときにも迅速に、適切な対応する必要があります。
今回の法律改正は、このような被害をなくすためのものです。
法律で規制されましたから、啓発もされますし、具体的な行政指導の根拠もできました。
パワーハラスメントで悩む人が居なくなるように、この法律改正が第一歩となり、さらなる対策が進められることを期待します。
トヨタ自動車との和解

2022年1月31日、トヨタ自動車株式会社で勤務していた男性の遺族が、2010年におきた男性の自殺に関して、トヨタ自動車株式会社と訴訟外で和解したことを発表した。
翌日の地元の中日新聞は、そのことを一面トップで大きく報じた。
本当に良かったと思う。ご遺族は11年も戦ってこられた。
労基署は労災と認めず、提訴したものの1審では敗訴であった。
つい昨年高等裁判所で逆転勝訴するまで10年間、負け続けた。
心が折れそうになったのではないかと想像する。
新聞報道によると、トヨタ自動車が謝罪し、和解したのは、行政の高裁判決があったからではあるが、それだけではないらしい。
高裁判決をうけて、会社内で調査し、パワーハラスメントの事実について遺族に伝えたとある。調査の結果も、トヨタ自動車が責任を認めなければならないないようだったのであろう。
もし、高裁判決が1審判決とおなじように、原告敗訴で終わっていたら、再度の調査もなく、真実がわからないままだったかも知れない。社長が謝ることがなかったかもしれない。
ご遺族と弁護団の諦めないでやり抜いたことが、裁判所を動かし、そしてトヨタを動かしたのだと思う。
亡くなられた男性の方に謹んで哀悼の意を表したい。そしてその死を教訓に、労働環境の改善がなされようとしていることを信じたい。
過労死の認定基準改定
2021年9月14日、過労死の認定基準が改定されました。
20年ぶりの改定でした。
ただし、いわゆる過労死ライン(直前の1か月100時間、直前の6か月の平均が80時間)が変わることはありませんでした。
過労死弁護団全国連絡会議のコメントは下記のリンクの通りです。
過労死110番 | いわゆる脳心臓疾患の労災認定認定基準改定についてコメントを出しました (karoshi.jp)
私個人としても過労死ラインについて見直されなかったのは残念です。このラインにわずかに届かないために労災認定されない事案もありました。
ただし、労働時間以外の要素がより細かく認められたことは評価できます。これによって、時間が100時間、80時間に届かない事例でも一定の場合に労災認定がなされることになりました。
これを踏まえて、労災認定を目指したいと思います。
2021年12月から、精神障害の認定基準についての専門検討会が始まりました。こちらも注目です。
謹賀新年2022

明けましておめでとうございます。
昨年は、新型コロナウイルス感染症の影響で、行動様式が変わったままの一年でした。
しかしながら、2年目で、弁護士の業務自体は、新しいやりかたで対応をしてきました。
法律相談、打ち合わせはかならず、マスク着用のままでお願いしました。
当事務所では、アクリル板を設定しないかわりに、CO2測定器を打ち合わせ室に備えて、常に換気の状況を見えるようにしております。
裁判は、弁論準備については、裁判所に行かずに、Web会議になりました。これによより、感染を予防しながら裁判が続行されました。
裁判員裁判は、法廷で行われましたが、マスクをしながら、対応しました。
民事の証人尋問も同様です。傍聴席が、一つおきになったり、マスク着用が必須になったりしていますが、裁判も動いています。
大学での授業も担当していますが、今年は、オンラインも取り入れつつ、学生さんに直接教室で授業をすることができました。
弁護士会の会議は、zoomで行われることが多くなりました。直接会って話すことができない分、特に人数の多い会議では発言はしにくいのですが、少人数の場合には、集まるのとそれほど変わらない感覚で会議ができました。移動時間がないこと、感染については安全であることメリットです。
コロナ禍がおわっても、これらの機器をもちいてハイブリッドで会議に参加するやり方は続けられると考えられます。
飲み会がなくなり、弁護士同士、友人、知人のあつまりすべてが疎遠になっています。そういうところで人間関係や仕事に少し変化が出ているかも知れません。
スマホの歩数計によると、2019年、2020年、2021年の1日に歩いた平均歩数を数えると、少しずつ減っています。こちらのほうが、意識して健康の維持にもつとめていきたいと思います。
残念ながら、世界ではまだコロナウイルスの感染状況は収束して居らず、あらたにオミクロン株という変異株が、広がっています。
まず、コロナウイルスの感染に気をつけて手洗い、換気に注意し、マスクを着用し、感染の可能性のある接触をしないように、気をつけて過ごしていきたいと思います。
そして、この生活は、まだ続くかも知れないことを頭に入れてすごしていきたいとおもいます。
また残念ながら、過労死の事件は起きています。それはこの新型コロナウイルスの影響を受ける前からの原因であったりするものもあります。コロナウイルスの影響するものがあります。そして、過労死の事件は時間がかかることが多く、コロナウイルスの感染の前に亡くなった方の事件も進んでいきます。
一つ、一つ解決へ向けて、必要なことを進めていきたいとおもいます。
過労死事件は、ことし判決や、行政の判断が予定されているものがあります。
適切な判断がなされるように期待しているところです。
加えて、昨年の脳・心臓疾患の労災認定基準が改定されました。今年は、精神障害の労災の認定基準の改定のために専門検討会が始まりました。過労死弁護団全国連絡会議では2018年に改定の意見書を求めているところです。この意見書の意見を取り入れて改定されるかどうか、専門検討会の議論の経過をしっかり見ていこうと思います。
2021年を振り返って
ことし1年。私が担当していないのですが、愛知県では、名古屋高裁の4月28日判決、9月14日判決がありました。いずれも、1審では労災と認められなかった事件が、高等裁判所で判断が覆りました。希望がもてる判断だと思います。
近年、認定基準の改定により、1980年代、90年代の事案に比べて、過労死等の認定はされやすくなりました。一方で裁判所の判断は画一的になってきており、行政の主張を追認するようになってきました。裁判で勝利することは難しくなっています。
そのなかで、この二つの判決は、理性的な判断で、行政の政策的な判断を覆し、司法の本来の意義を果たした判決といえます。
私自身も、労災認定を得て記者会見をできた事件もありました。
また、長く争ってきた過労死事件がいくつか解決しました。ご家族にとっては、大切な人が亡くなったことにかわりがありませんが、一つの区切りにして進んでいっていただければと思います。
一方で、新たな事件の相談もありました。今年、亡くなった方の事件もありました。過労死がなくなっていかないことを残念に思います。救済のために尽力したいと思います。
引き続き判断を待っている事件があります。年度末に向けて、良い判断がなされるようにと願っています。
脳・心臓疾患の認定基準が改定されました。これまでよりも、労働時間以外の事情も考慮される内容になっています。これを生かして判断してもらうように努力していきたいです。
さらに、精神障害の認定基準の専門検討会が始まりました。これまでの認定基準に不当なところが改定されるように努力していこうと思っています。
これらの認定基準の改定により、救済されるべき人が、早期に救済されなければなりません。
トヨタ自動車(豊田労基署長)事件 2021年(令和3年)9月16日判決
名古屋高等裁判所は2021年(令和3年)9月16日、トヨタ自動車の従業員が自殺下事件について、労災と認めなかった名古屋地方裁判所の判決と取消し、豊田労基署長の労災と認めなかった判断を取り消す判断をした。
労災だと訴えていた遺族の訴えを認めて逆転勝訴をさせた。
私は、弁護団ではなく、この事件については詳細は把握していないが、諦めないで、裁判を戦ったご遺族の方、そして、弁護団の水野幹男弁護士、梅村浩司弁護士、加計奈美弁護士に心から敬意を表したい。
この労働者の自殺は2010年(平成22年)のことであるから11年が経過して、ようやく労災であると認められたのであり、ご遺族の苦労は計り知れない。
判決では業務に関して次のような心理的負荷が指摘されている。
「達成は容易ではないものの、客観的にみて努力すれば達成可能であるノルマが課され、この達成に向けた業務を行った。」と評価できることが「中」
「弱」であるが、他の業務と並行して上記業務を進行させる責任を負っていたという点において相応の心理的負荷があったと考えられる出来事がある。
はじめての海外業務を担当することについて「仕事の内容の大きな変化を生じさせる出来事があった」に該当する精神的負荷があった。(心理的負荷としては「中」相当)
そして、パワーハラスメントについては次のように認定されている。
グループ長から、他の従業員の面前で、大きな声で叱責されたり、室長からも、同じフロアの多くの従業員に聞こえるほど大きな声で叱りつけられたりするようなことは,軽視できない。同様な叱責を受けていた○○をして、後日、本件会社の退職を決意させる有力な理由となるほどのものである。
このような事実を否定したグループ長、室長の証言は、他の証言等を理由に信用できないと退けられている。
そして、このパワハラを、2020年に改定された精神障害の労災の認定基準に当てはめをして
「他の労働者の面前における大声での威圧的な叱責」であり、その「態様や手段が社会通念に照らして許容される範囲を超える精神的攻撃」と評価されるのが相当である。
と判示した。
さらに、その叱責は少なくともグループ長から週1回程度、室長から2週間に1回程度だったと認定している。
心理的負荷については、次のように判断している。
個々的にみれば「中」には相当する。
それらの精神的攻撃は、グループ長のみならず、室長からも加えられている。
そして、これらの行為は、平成20年末頃から本件労働者が発病に至るまで(発病は平成21年10月頃とされている)反復、継続されている。
判決は、これらの事実を踏まえ、
一体のものとして評価し、継続する状況は心理的負荷が高まるものとして評価するならば、上司からの一連の言動についての心理的負荷は、「強」に相当する。
と判断している。
判決は、
上記の出来事の数及び各出来事の内容等を総合的に考慮すると、平均的労働者を基準として、社会通念上客観的にみて、精神障害を発病させる程度に強度の精神的負荷を受けたと認められ、本件労働者の業務と本件発病(本件自殺)との間に相当因果関係があると認めるのが相当である。
と判示した。
この事案、リーマンショックの後で、時間外労働は厳しく制限しており、当該労働者もほとんど時間外労働は行っていない。
しかし、業務の変化の大きさや,パワーハラスメントの実態を認めて、業務上の疾病と認めている。
1審判決は、パワーハラスメントについて、
「本件労働者に対する業務指導の範囲を逸脱しており,その中に本件労働者の人格や人間性を否定するような言動が含まれ,あるいはこれが執拗に行われたものとは認められない。」
として、その心理的負荷が「強」とは認めなかった。
改正前の認定基準では、「人格や人間性を否定するような言動が含まれ」ていなければ、心理的負荷が「強」にはならないかのようにされていた。
判決からは、当のパワハラをしていたという上司の証言の信用性は否定されているが、パワハラをした当人が、そのことを全く認めないというケースは、私にも経験がある。これを立証するのは、なかなか困難である。現に1審判決は控えめな評価で労災と認めなかった。
高裁の事実認定をみても、原告側でいろいろな角度から立証の努力をしたのだろうと推測される。当事者と弁護団の相当の努力が会ったのだと考えられる。
これを記載している9月19日は、上告、上告受理申立の期間内ではあるが、事実認定が大きな争点であるから、上告、上告受理申立理由はなく、被告国も上告、上告受理申立はしないのではないかと予想される。
損害賠償請求訴訟が別に1審に係属している。被告トヨタ自動車株式会社は、労災が認定された事案とは異なり、本件では、争う姿勢を見せているようであるが、高裁判決がパワハラ等を認めて労災であると判断したのであるから、これを尊重し、早期に全面的な解決に向けて態度を変更するべきである。
2021 過労死等防止対策推進シンポジウム
2021年も、厚生労働省主催の過労死等防止対策推進シンポジウムを開催します。
愛知会場は、高橋幸美さん(電通で過労自死した高橋まつりさんのお母様)と、その事件を担当した、川人博弁護士がお話をされます。
これらの話を通じて、過労死の問題について考えます。
今年は、コロナウイルス感染症の問題がありますので、予約制です。参加するためには申込みが必要です。
すでに、申込みが多く、早めに予約した方が良さそうです。
なお、この過労死防止対策推進シンポジウム、会場によっては、お名前を公表したくないご遺族がお話をされるところもあります。
そのため、コロナウイルス感染があっても、オンラインでは開催することが難しいようです。
愛知会場は
11月8日月曜日午後2時から
このころには、コロナウイルス感染症の拡大が収まって、感染対策をしながらの会場開催ができるように祈っています。
是非ご予定下さい。
↓申込みは下記からです。
厚生労働省がパブリックコメント募集中
2020年6月、脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会が厚生労働省に設置されました。そこで、2001年に発出された脳・心臓疾患の労災認定の基準について、検討がなされてきました。
2021年7月、脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会の報告書が公表されました。
これにもとづいて2021年9月頃、あたらしい認定基準が策定されようとしています。
新しい認定基準の概要はパブリックコメントの頁に掲載があります。これについて、現在、パブリックコメントの募集がなされています。期限は本年8月19日まで。
2001年から20年ぶりの認定基準の改定です。
これまで、仕事が原因ではないかと考えられる事案でも時間外労働時間が少ないために認定されず、裁判になった事案がありました。
幸い、訴訟において認定されることになった事案もありますが、認定されなかった事案もあります。
より適切なないようになるように、さらに毛一歩声を上げたいと思います。




